
―自然共生型環境の形成と環境教育について―
名古屋造形芸術大学・短期大学
岡田憲久 森田紘 品川誠 村越昭彦

はじめに
本研究は1996年の特別研究「造形の杜」を契機として始まり、教育環境としての学内をより緑豊かな環境としたいと言う思いで発足したものが発展展開し、1999年、2000年、2001年の3ヵ年による本研究へと繋がったものである。
本学周辺は、非常に豊かな自然環境に恵まれているように見えながらも、産業廃棄物の処分場が緑の環境の中に何箇所も散在し、都市の歪ひずみが随所に見られる今日の環境である。自らの置かれた環境が、教育環境としてどのような環境にあるのかをより正しく把握し、地域性が持つ豊かな自然と文化遺産を背景としたこの地における教育の在りかたを模索しようとするものである。さらには地域が抱える都市のひずみとしての今日的社会的問題へのアート、デザインの世界から作品として探求する事へとつなげたい。以上のことを日々の教育環境の形成と日々の教育の中で行えないかを模索するための序章である。
 産業廃棄物の処分場
産業廃棄物の処分場
キャンパスの自然環境の把握として樹木調査図の作成
本学がこの地に移転したのは1985年であり、名古屋市中村区稲葉地から移設した当時は、丸裸の大地の上の校舎群であった。11haの敷地面積があり、残された自然林はわずか 15000㎡であった。
我々研究チームは、芸術系大学の学生たちの豊かな感性を育む教育環境として、生き物の一員である人間が様々な生命体と共にあることを、日常の中で感じ取れる環境であることが非常に大切であると言う考えのもとに、創設時の植栽さらには既に始まっていた卒業時における記念植樹等による緑化をさらに充実させるため、まずキャンパスの現在の自然環境の把握として、土壌調査を行い、さらに現況樹木調査図の作成を行った。
杜をつくる
樹木調査図をもとに、キャンパスの緑化計画として大きく2つのゾーンの設定を行った。まず第一は地域の自然植生に復元するゾーン(残された2次林の復元拡大)。もうひとつは修景的植栽ゾーンである。キャンパス敷地に残る自然林は、ヤブツバキクラス域代償植生のコナラークリ群落と呼ばれる植生であり、コナラの植被率の高い林相である。
卒業式の記念植樹の機会を中心として、自然植生復元ゾーンではコナラを中心とした苗木植栽、キャンパス敷地内のコナラのどんぐりを拾い植栽するどんぐりを植栽し荒地を緑の環境に変えていく試みを行ってきた。
土をつくる
杜を作るための背景造りとして、やせた台地、貧困な土壌環境からわずかにでも生まれる有機物としての剪定枝、刈り草の学内でのリサイクル化を行い、新たに植栽する基礎土壌とすることを行った
キャンパスを生命環境としての作品づくりの場に
大学キャンパスを日々成長する生物集団として捉え、生態的自然環境を背景として、そこで日々時間を費やす教員、学生が、生物集団の一員として自らの教育環境、作品の制作環境を、巣づくりのように自らが作って行く状況づくりをおこなおうとしている。
その一つが、日常の学生たちの日々の制作テーマとの連動である。
ビオトープ:卒業制作で一人の女の子が一人で土を掘ってビオトープを完成させた。
絵本づくり:村越先生の授業で学内の自然をテーマとした絵本づくりが行われた。

 ビオ・トープ
ビオ・トープ
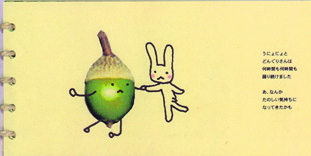 自然をテーマとした絵本
自然をテーマとした絵本
部活との連動
キャンパスのあるゾーンをレンゲソウやクローバー、オオキンケイギク、シャスターデジーなどのワイルドフラワーにより、より豊かなみんなが興味を示す、愛される環境に変えて行く事を行った。
地球部という部活が発足された。これはオーストラリア人ビル・モリソンにより提唱されている「農業に携わり生活することは、人間としての永久的文化生活に繋がる」というパーマカルチャーと呼ばれる思想を具現化するものである。地球部はキャンパスの一部を耕し、スイカ・サツマイモ・ジャガイモ・トマトなどを生産している。その活動はさらに地域社会にも拡大され、地域の稲刈り田植えに参加している。


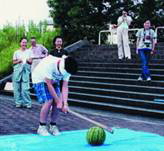
タケノコ掘り スイカの収穫
環境教育としての自然学講座
キャンパス内の自然環境を整えていくために、本来の自然とはどのようなものなのか、その自然に対して我々はどのようなことをしてきたのかを知るための環境教育の場の設定を大学短大の枠を越えたゼミとして「自然学講座」を行っている。
・社会的問題となっている環境の現地踏査
藤前干潟
海上の森 里山
・自然の根源の姿を体感学習する原生林を歩く講座
1997年夏 八ヶ岳白駒池原生林 モミ、ツガの針葉樹林帯
1998年夏 京都大学 芦生原生林 裏日本型ブナの原生林
2000年夏 岐阜大学 演習林 表日本型ブナの原生林
2001年夏 京都大学 芦生原生林
2001年夏 京都大学 芦生原生林
 芦生原生林
芦生原生林
地域環境の把握
大学周辺の地域環境の把握のために、大学を中心とした南北8㎞、東西5㎞の区域(北は博物館明治村、中央道小牧東インター、南は東名高速道春日井インターの入る範囲)の1999年(平成11年)4月撮影の航空写真を入手した。それをオルソー画像処理(21枚の画像をコンピューターで正射投影処理)と呼ばれる手法によりにより1:5000の画像としてパネル化をおこない、多くの人が視覚的に認識しやすい基礎資料とした。
さらに自分たちの日々生活する大学キャンパス周辺の地域環境の把握を環境教育の基礎として捉え、人間と自然の関係の結果としての地域の自然・文化環境を解りやすく把握でき出かけることができるように、手引きのイラストマップの制作を行っている。助手の伊藤聖子さんのイラストをベースに中島裕之さんのデザインにより現在その最終作業を行っている。
自然文化誌マップとして地形、地質、植生、指定文化財、埋蔵文化財の位置と簡単な説明を記したマップとなっている。学生たちがこのマップを手に地域に出かけ更なる情報がここに書き加えられこの画像が更新されて行けばと考えている。
おわりに
今後更なる植栽環境生育の充実をおこない、それを背景としたキャンパスの教育環境が学生たちの作品活動、さらには日々の部活などの諸活動との連動性へと拡大充実が図れればと思っている。